金融トラブルに巻き込まれないために②金融商品や金融取引にまつわる法律・ルールを知ろう!クーリングオフ制度、貸金業法、生活防衛資金とは? 【第49話】
金融取引の基本としての素養 #2
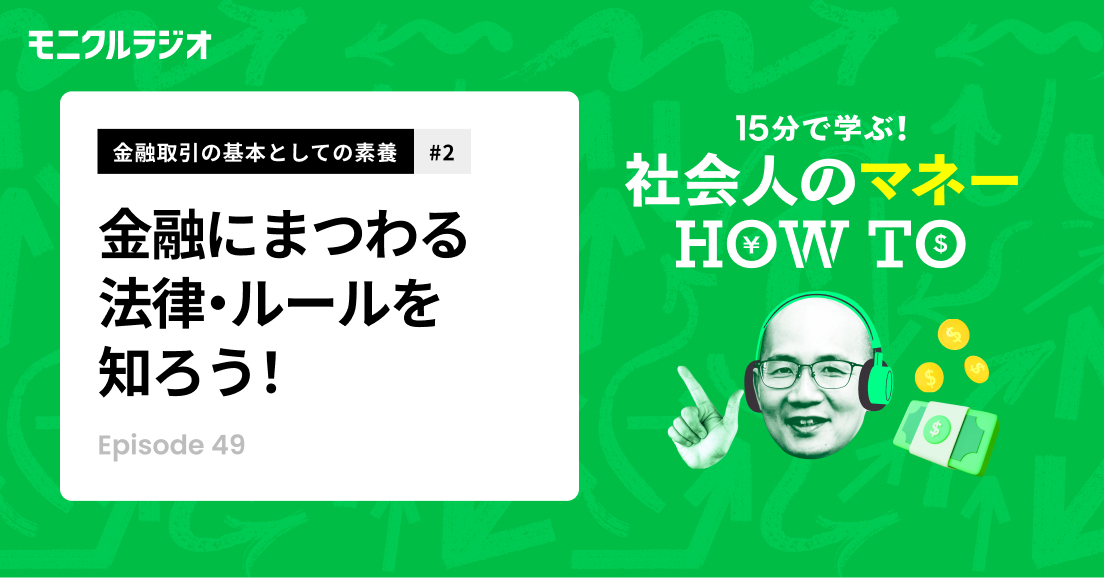
ポッドキャストを聴く(金融取引の基本としての素養 #2 金融トラブルに巻き込まれないために②金融商品や金融取引にまつわる法律・ルールを知ろう!クーリングオフ制度、貸金業法、生活防衛資金とは? 【第49話】)
はじめに
音声メディア『モニクルラジオ』がお届けする金融教育ポッドキャスト「15分で学ぶ!社会人のマネーHOW TO」は、「これだけおさえておけば、お金で大ケガをしない!」をコンセプトに、全50回のプログラムを配信しています。この番組では、学校の金融教育カリキュラムを作る際にも使用されている「金融リテラシー・マップ」にまとめられている項目を踏まえながら、金融知識をひとつずつ学んでいきます。
今回は、第49回の「金融取引の基本としての素養 #2 金融トラブルに巻き込まれないために②金融商品や金融取引にまつわる法律・ルールを知ろう!クーリングオフ制度、貸金業法、生活防衛資金とは? 【第49話】」でお話しした内容を記事としてお届けします。
金融にまつわるルールを知ろう
今日のテーマは「金融商品や金融取引に関わるルール」です。
前回扱った詐欺などのトラブルを避けるために、知っておくと役立つ知識を解説します。
まず大前提として、トラブルを防ぐには、国に認められた正規の金融機関と取引することが重要です。
日本では、銀行・証券会社・保険会社などの金融機関や金融事業者は、国の免許を取得して営業することが法律で定められています。
つまり、免許のない事業者は、日本国内で金融関連の商品を売買したり仲介したりすることができません。
金融庁に「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」リストが掲載されているので、証券口座を開く際は調べてみると安心です。
また、各社のHPなどにも、必ず「登録番号等」などの形で記載があります。
免許制ということは、正規の金融事業者は国のお墨付きということですね。
その通りです。海外の会社が日本で金融業を営むときにも、日本国の免許が必要です。
ちなみに、時々「金融庁による行政処分」という報道がありますよね。
はい。報道で見かけますね。
免許制の金融業者は、基本的に金融庁の管轄下にあり、国が監督責任を負っています。
各社の経営状況・財務状況・コンプライアンスの遵守など、さまざまな観点で金融庁が企業の運営状況を監視しています。
金融庁のサイトにいくと、このような記載があります。
- 明確なルールに基づく透明かつ公正な金融行政の徹底
- 利用者保護と市場の公正性の確保に配慮した金融のルールの整備と適切な運用
「法律を守って契約者に不利益がない運営をしているか」「市場の公正性を守っているか」という観点で、監視しているんですね。
「金融庁が業務改善命令を出した」といった報道を目にすることもあります。
そうですね。政府が監督を行いながら、必要に応じて法律の改正なども進めてきた歴史があります。
詐欺がきっかけ?法改正の歴史
例えば、保険の回で触れた「少額保険」という制度があります。この制度ができた背景には、1997年に起きた詐欺事件(オレンジ共済組合事件)がありました。
オレンジ共済という無認可の共済組合が、約2000人から90億円以上を集めたといわれています。高めの金利を提示し、最初は配当金を支払うなど、巧妙な手口でお金を騙し取った事件です。
当時は規制がなかったため、この事件に限らず無認可の共済が多く設立され、詐欺も多発していました。こうした状況を受けて、法律が改正されたんです。
金融に関わる事業者が認可を受けているかどうかは、とても重要なポイントですね。
先日、金融庁が暗号資産(仮想通貨)に関する法律の改正を検討し始めたという報道がありました。
代表的な暗号資産には「ビットコイン」「イーサリアム」などがあります。暗号資産は、現状では決済手段として「資金決済法」の対象であり、金融商品には含まれないため「金融商品取引法」は適用されません。
もし暗号資産が金融商品取引法の対象となれば、暗号資産を扱う事業者の経営状況や情報開示が透明になり、利用者にとって安心して取引できるというメリットがあります。
また、株式や投資信託のように金融商品として扱われる場合、課税区分は雑所得ではなくなり、所得税率は約20%に抑えられます。現在の制度では、暗号資産による利益には、最大で55%の税率がかかる場合があります。
法改正によってメリットがあるのは理解できますが、やはり詐欺の抑制につなげることが重要ですよね。現状でも注意喚起が行われていますが、無登録業者による取引詐欺は増えているともいわれていますよね。
そうですね。暗号資産に関連する詐欺事件も多発しています。また、法規制による罰則の強化が検討されているとの報道もあります。
暗号資産は、将来的に「暗号資産のETF」として金融商品化が検討されています。今回の法改正の議論には、そうした狙いもあるといえるでしょう。
現在、暗号資産は口座開設数が1000万を超え、預託金残高が5兆円以上になっています(2025年1月時点)。NISAは口座数が2560万(2024年末時点)なので、暗号資産の市場規模もそれなりに大きいといえるでしょう。
ですが、現状の暗号資産は、資産形成の手段としてあまり推奨できません。
投資そのもののリスクに加え、円やドルなどの法定通貨と違い国や中央銀行が発行するものではないため、制度面でのリスクも大きいといえます。
クーリングオフと金融商品の販売ルール
制度でいうと、クーリングオフ制度というものも聞いたことがあります。
クーリングオフ制度も、訪問販売によるトラブルが増えたことを受けて制定されました。
契約書面を受け取ってから一定期間内(原則8日間や20日間など)であれば、購入契約を撤回できる制度で、特定商取引法に定められています。
電話勧誘販売や学習塾、エステなどの「特定継続的役務提供」に該当する場合など、適用される取引内容が定められています。
普通の店舗での買い物は、クーリングオフ制度は該当しないのでしょうか。
はい、普通の店舗での対面販売は適用外です。ECショッピングを利用される方も多いと思いますが、こちらも原則適用されません。
もちろん、一般的には各サイトや店舗によって返品規約が定められているので、「クーリングオフがないから買ったら終わり」というわけではありません。とはいえ、買い物も契約であり、返品を前提とするものではありませんが。
金融商品でいうと、保険商品は原則、クーリングオフ制度が適用されます。一方で、投資信託や上場株式などの有価証券は、クーリングオフの対象外です。
金融商品でも、商品ごとにクーリングオフのルールが異なるんですね。
はい。金融機関には「元本割れリスク」などの重要事項を、購入者(契約者)に説明する義務があります。
「ほとんど預貯金がなく、投資も初めて」というような、金融リテラシーがあまりなく投資をするリスクが高い人には、投資信託などの販売が禁じられています。
「生活防衛資金」といって、万が一働けなくなったときなどに備えておくべき生活費は、確保しておく必要があるためです。
万が一、金融機関がこれを怠った場合は「金融商品販売法」や「消費者契約法」に則り、行政処分などの罰則が課されます。購入者が損害を被った場合は、損害賠償請求ができたり、契約を破棄できることもあります。
返済能力を超えた貸付けを禁止する「貸金業法」
トラブルから消費者を守るために、多くの法律や制度が作られてきたんですね。
最後に、金融トラブルを防ぐための法律をもう一つ紹介します。「払いきれないほどの借金を防ぐ」という観点から定められているのが「貸金業法」です。
年収の3分の1までしかローンを組めないなど、高額な借入れを防ぐためのルールが設けられています。これは「総量規制」と呼ばれ、返済能力を超える貸付けを禁止する仕組みです。
また、信用情報機関には個人のローン状況が登録されており、その情報をもとに貸付けが管理されています。
ただし、クレジットカードでの買い物や、銀行からの借入れは、この規制の対象外です。銀行はそもそも貸金業者には含まれないためです。
貸金業者とは、「消費者金融」「事業資金を貸付ける事業者金融」「クレジットカード会社」などです。
結局のところ、自分のお金の全体像を正しく把握できるのは、自分自身しかいないということですね。
はい。国の認可を受けている金融機関でお金を借りても、借金が増えすぎると「多重債務」といって、自分では返しきれない借金を背負ってしまうリスクがあります。
例えば、住宅ローンを組んで、銀行で個人的にローンを借りて、クレジットカードで買い物をしすぎてリボ払いや分割払いをして、ということが重なると、借金が膨らむリスクがあるでしょう。
基本的な考え方として、
- 自分の収入を把握する
- 収入の中で生活できるよう計画を立てる
これが原則です。無理な投資も避けましょう。
以前に家計管理の回で、「可処分所得を把握して、固定費や流動費を把握することが大切だ」とお伝えしましたが、その考え方ともつながっている話です。
金融のいろいろな知識を学んでから振り返ると、最初の方で学んだ「家計管理」「ライフプランニング」の大切さ、重要さが分かりますね。
万が一、多重債務になってしまった場合は、「自己破産」で借金から解放される制度もあります。
ですが、そうなると信用情報にも関わりますし、住宅ローンなどを数年間組めなくなったり、クレジットカードを作れなくなるなど、いろいろな制約も出てしまいます。
いろいろな事情があるとは思いますが、強くいっておきたいのは、ヤミ金や闇バイトといわれるものは犯罪にも関わり、命の危険もあります。そこには絶対に近づかないことです。
今日ご紹介したいろいろな法律によって、金融取引は守られていますが、金融リテラシーを高め、知識をアップデートすることが自分を守るためにも大切です。
第49話のまとめ
- 日本の金融機関や金融事業者は、国に免許をもらい営業することが法律で定められている
- 免許の有無は、金融庁HPに公開されている「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」リストで確認できる
- クーリングオフ制度、貸金業法など、金融トラブルを避けるための制度や法律が定められている
- 多重債務は危険。金融リテラシーを高め、無理なお金の使い方はしないのが原則。無認可の金融業者には絶対に近づかないこと
パーソナリティー:泉田良輔プロフィール
株式会社モニクル
取締役 グループ戦略担当
泉田 良輔 Ryosuke Izumida
慶應義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。2013年3月、株式会社ナビゲータープラットフォーム(現:株式会社モニクルリサーチ)を共同設立し、取締役に就任(現在は代表取締役)。2018年11月、株式会社OneMile Partners(現:株式会社モニクルフィナンシャル)を共同設立し、取締役に就任。2021年10月、ナビゲータープラットフォームとOneMile Partnersの親会社として、株式会社モニクルを設立し、取締役に就任。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。東京科学大学大学院非常勤講師。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程修了。著書に「銀行はこれからどうなるのか」「Google vs トヨタ」「機関投資家だけが知っている『予想』のいらない株式投資法」など。












