iDeCo制度を知ろう!②制度を利用できるのはどんな人?税制メリットがあるってどういうこと?【第34話】
金融分野共通#20
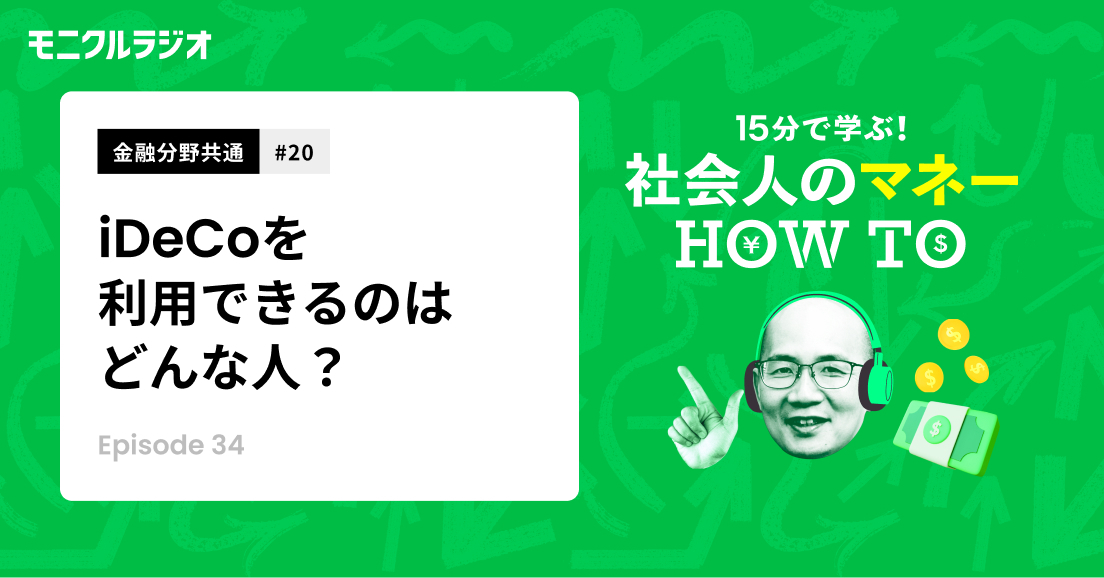
ポッドキャストを聴く(金融分野共通#20 iDeCo制度を知ろう!②制度を利用できるのはどんな人?税制メリットがあるってどういうこと?【第34話】)
はじめに
音声メディア『モニクルラジオ』がお届けする金融教育ポッドキャスト「15分で学ぶ!社会人のマネーHOW TO」は、「これだけおさえておけば、お金で大ケガをしない!」をコンセプトに、全50回のプログラムを配信しています。この番組では、学校の金融教育カリキュラムを作る際にも使用されている「金融リテラシー・マップ」にまとめられている項目を踏まえながら、金融知識をひとつずつ学んでいきます。
今回は、第34回の「金融分野共通#20 iDeCo制度を知ろう!②制度を利用できるのはどんな人?税制メリットがあるってどういうこと?【第34話】」でお話しした内容を記事としてお届けします。
iDeCoに加入できる人とは
今回は、前回に続き「iDeCo制度」について解説していただきます。
これからお話しする内容は、あくまでも収録時点での内容となります。iDeCoの加入条件や掛け金の上限などは、前提条件によって異なりますので、詳細は厚生労働省のHPなどでご確認ください。
先日、「iDeCoの掛け金の上限が上がる」というニュースを見ました。つまり、iDeCoで資産形成に使える金額が増えるということでしょうか。
その通りです。2025年の税制改正で26年1月から掛金の上限引き上げが盛り込まれています。現時点では決定というニュースは出ていないですが(※25年8月時点)、もしそうなれば「iDeCoの節税メリットを活かしながら、資産形成できる金額が増える」ということですね。
新NISA制度も掛け金の上限額が決まっていて、つみたて投資枠は年間120万円まで、成長投資枠は240万円まででした。iDeCoの掛け金についても教えてください。
以前、「iDeCoは年金制度の一部であり、私的年金である」というお話をしました。新NISA制度と異なるのは、仕事の仕方や勤務先によって、掛け金の年間上限額が異なる点です。
まずは「iDeCoに加入できる人」をカテゴライズしていきましょう。
iDeCoを利用できるのは現状は「20歳以上65歳未満」の会社員や公務員、また60歳未満の自営業者やフリーランス、専業主婦/主夫です。このように、国民年金の概念と連動しています。
国民年金には「第1号被保険者」「第2号」「第3号」という分け方があります。それぞれ、どのような人があてはまりますか?
第1号は「自営業、学生」などです。第2号は「会社員や公務員」など、第3号は「第2号の配偶者」ですね。
第1号と第3号は「20歳以上60歳未満」と加入年齢が決まっています。
第2号は「70歳未満」の方があてはまり、20歳未満でも会社員や公務員であれば該当します。また、年金制度の2階建て部分である「厚生年金」の対象でもあります。
iDeCoに加入できるのは、第1号(自営業や学生)と第3号(第2号の配偶者)は20歳以上60歳未満の方。第2号(会社員や公務員)は20歳以上65歳未満の方。ただし、第2号であっても20歳未満の方は、iDeCoは利用できないということですね。
その通りです。「第1号~3号」という区分と、iDeCoの対象者はイコールではありませんが、紐づけて考えておくと理解しやすいと思います。
また、区分によって掛け金の上限額が変わります。第2号被保険者の場合は、勤務先の企業年金の加入有無によって細分化され、年間24万円から81.6万円の間で、人により金額が異なります。
では、第1号被保険者のケースから教えてください。
第1号被保険者の学生や自営業の方は、年間の掛け金の上限は81.6万円(月額6.8万円)です。ただし、国民年金基金とそこに付随する付加保険料との合算で計算されます。
国民年金基金は、自営業やフリーランスの方などを対象とした年金で、会社員の厚生年金のようなものです。国民年金の第1号被保険者のための年金、二階建ての部分にあたります。
次に、第2号被保険者の場合について教えてください。
会社員や公務員の方は、お勤め先が「企業年金」に加入しているかどうかで分けられます。
企業年金がない場合、年間の上限額は27.6万円(月額2.3万円)です。
勤め先が何らかの企業年金に加入している場合は、計算が必要です。iDeCoの月額上限額(5.5万円)から企業年金の掛け金を差し引いた額がiDeCoの掛け金の上限となります。(※選択制企業型DC、企業型DC及びDBに加入している場合のiDeCoの上限は2万円となります。)
第2号の方は、企業年金の加入有無の確認が必要ですね。
ちなみに、企業年金には、企業型DCと呼ばれる「企業型確定拠出年金」、DBと呼ばれる「確定給付企業年金」などがあります。iDeCoは「個人型確定拠出年金」ですね。
会社員の場合は、企業型DCのみや、企業型DCとDBを併用している場合もあります。
それでは、第3号被保険者の場合についてもお願いします。
第3号被保険者、つまり第2号被保険者の配偶者の方は、年間の上限額は27.6万円(月額2.3万円)です。企業年金に加入していない第2号被保険者の方と同じ金額です。
iDeCoの3つの税制優遇とは
iDeCo制度に加入すると税制メリットがあると聞きますが、詳しく教えてください。
iDeCo制度では、3つのタイミングで税制の優遇を受けることができます。
iDeCoでは、支払いから受け取りまで、何らかの形で税制優遇を受けられるんですね。
まず、「掛け金を支払うとき」は、掛け金が全額「所得控除の対象」となります。
「運用しているとき」は、運用によって得た利益である「運用益」が非課税となります。
金融商品の運用益には、通常約20%の税金が発生します。新NISA制度の運用益にはこの税金は発生しないという話でしたが、iDeCo制度も同様なんですね。
その通りです。以前に、新NISA制度との違いとしてお話ししましたが、iDeCo制度は商品の「スイッチング」が可能です。投資している金融商品を売却したら、すぐに別の商品を買うことができるんです。
非課税なのでiDeCo口座内で運用益をどんどんプラスにして、運用益分を別の商品に再投資する、ということも可能です。
60歳になるまでiDeCoからお金を取り出せなくても、iDeCoの中で利益を増やしながら運用して、どんどん老後資産を増やしていけるんですね。
はい。そこが新NISA制度にはない、iDeCoのメリットだと思います。
iDeCoの受け取り方と金融機関選びのポイント
60歳を過ぎて、「給付金」としてお金を受け取るときにも、税金の控除があるんですね。
iDeCoで運用して受け取るお金のことを「老齢給付金」といいます。企業型DCも同様で、確定拠出年金制度で受け取る年金のことですね。
この老齢給付金は、確定拠出年金制度に加入していた年数によって受け取れる年齢が異なります。最短の60歳から受け取りたい場合は、60歳になる前に10年以上加入している必要があります。
詳しい条件は、iDeCoの公式ページで調べられますよ。
老齢給付金は、どのように受け取るのでしょうか。
iDeCo制度の老齢給付金の受け取り方には、3パターンあります。
- 「年金」として、毎年一定額を受け取る
- 「一時金」として一括で受け取る
- 受給権が発生したら、一部を「一時金」で受け取り、残りを年金として毎年受け取る
年金として受け取ると「公的年金等控除」の対象で、一時金として受け取ると「退職所得控除」の対象になります。
受け取り方もカスタマイズできるんですね。iDeCo制度はどこで加入できるのでしょうか。
銀行、証券会社、保険会社などの金融機関が、iDeCoの運営管理機関となっています。新NISA制度と同じように、金融機関ごとに手数料や取扱商品のラインナップが異なります。
NISAとiDeCo口座は、同じ金融機関で開設することはできますか?
できます。ただし同じ口座ではなく、NISA用とiDeCo用の口座に分けられます。口座は一人一口座で、別の金融機関へ変更することも可能です。
同じ金融機関で開設した方が良いのでしょうか?
一概にいえませんが、iDeCoの取り扱い商品数や種類は金融機関によってかなり異なり、NISAよりも金融機関ごとの差がある印象です。
「NISAを先に始めたが、同じ金融機関のiDeCoには欲しい商品がない」となると、別の金融機関で口座開設した方が良いかと思います。ちなみに私は商品ベースで決めたので、iDeCoとNISAは別の金融機関です。そういう選び方もありますね。
第34話のまとめ
- iDeCo制度を利用できるのは、現状では「20歳以上65歳未満」の会社員や公務員方、また60歳未満の自営業者やフリーランス、専業主婦/主夫
- 掛け金の上限は、年間24万円~81.6万円の間。人によって異なるので要確認
- iDeCo制度には「掛け金の支払い時・運用中・給付金の受け取り時」に税制メリットがある
- NISAとiDeCoは同じ金融機関でも口座開設できるが、商品ラインナップが金融機関によって異なる。商品ベースで決めて分けるのもあり
パーソナリティー:泉田良輔プロフィール
株式会社モニクル
取締役 グループ戦略担当
泉田 良輔 Ryosuke Izumida
慶応義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。2013年3月、株式会社ナビゲータープラットフォーム(現:株式会社モニクルリサーチ)を共同設立し、取締役に就任(現在は代表取締役)。2018年11月、株式会社OneMile Partners(現:株式会社モニクルフィナンシャル)を共同設立し、取締役に就任。2021年10月、ナビゲータープラットフォームとOneMile Partnersの親会社として、株式会社モニクルを設立し、取締役に就任。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。東京科学大学大学院非常勤講師。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程修了。著書に「銀行はこれからどうなるのか」「Google vs トヨタ」「機関投資家だけが知っている『予想』のいらない株式投資法」など。












