株式を知ろう!①株式は、企業が資金調達する手段?株主優待はおまけ?【第36話】
資産形成商品#7
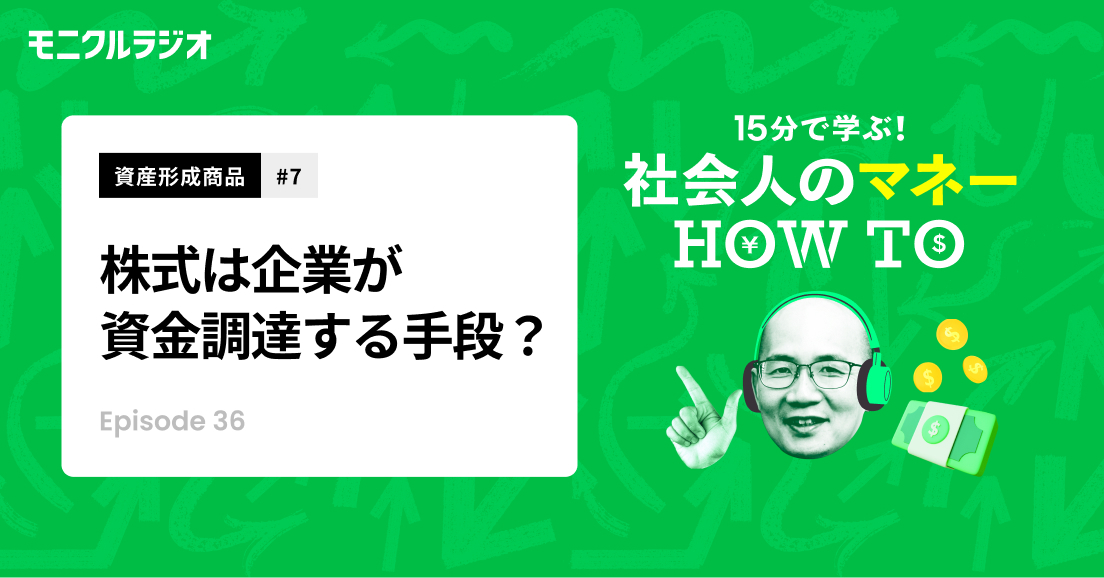
ポッドキャストを聴く(資産形成商品#7 株式を知ろう!①株式は、企業が資金調達する手段?株主優待はおまけ? 【第36話】)
はじめに
音声メディア『モニクルラジオ』がお届けする金融教育ポッドキャスト「15分で学ぶ!社会人のマネーHOW TO」は、「これだけおさえておけば、お金で大ケガをしない!」をコンセプトに、全50回のプログラムを配信しています。この番組では、学校の金融教育カリキュラムを作る際にも使用されている「金融リテラシー・マップ」にまとめられている項目を踏まえながら、金融知識をひとつずつ学んでいきます。
今回は、第36回の「資産形成商品#7 株式を知ろう!①株式は、企業が資金調達する手段?株主優待はおまけ? 【第36話】」でお話しした内容を記事としてお届けします。
株式の基本をおさらい
今日のテーマは「株式」です。
株式については、以前インデックスファンドの回でも触れましたが、改めてどういうものなのか整理していきましょう。さっそくですが、株式にどのようなイメージがありますか?
株式は、「株式会社が発行している投資商品」というイメージです。株主優待という言葉もよく耳にします。
そうですね。改めて定義すると、「株式会社が企業として資金調達するために発行する証券」が株式です。
株式も「有価証券」の一つですよね。
その通りです。上場企業は、さまざまな情報開示義務を負っています。例えば「有価証券報告書」という、企業の事業状況や財務状況などをまとめた文書を、内閣総理大臣に提出する義務があります。
「有価証券報告書」や「決算短信」はIR情報に掲載されていますね。
有価証券報告書には、投資家に開示義務があるすべての項目が掲載されています。企業の概況や事業の状況など、投資判断に役立つ内容が網羅されているんです。
財務状況だけでは、「この企業の投資を続けるか、やめるか」「投資金額を増やすかどうか」ということは判断できません。
泉田さんはフィデリティ投信在籍時に、金融機関として企業に投資されていましたよね。
はい。速報的な内容は決算短信で確認し、より詳しく企業を掘り下げたいときは有価証券報告書を参考にしていました。より細かい情報は、決算説明会資料を参考にすることもあります。
そうした情報をもとに、IR(投資家向け広報)担当者や経営者に取材を行います。事業構造などを深掘りしてヒアリングすることで投資判断をしますが、とても面白かったですよ。
ちなみに、有価証券報告書は株式だけではなく、債券(社債)に投資する投資家にとっても重要な情報源になります。
機関投資家だけではなく、個人投資家にとっても、投資判断をするために参考になる情報がたくさん載っているということですね。
その通りです。以前に解説した内容の復習ですが、投資信託はいろいろな会社の株式がミックスされていて、自分で厳密に分析しなくても投資判断ができるように設計されています。
一方で、いわゆる「個別株」「個別銘柄」という形で、特定の企業の株式を購入する場合は、有価証券報告書を読み込めることが理想です。
ですが、「この会社がなんとなく好きだな」という応援の気持ちで株式を買う方もいらっしゃると思います。
「よく行くカフェを経営している企業を応援したい」とか、「この企業のプロダクトのセンスが好き」「この企業は最近勢いがあるので買っておこう」というようなことですね。
身近な企業の場合、「この企業は良いな」という感覚を、自分の体験として実感できますよね。
例えば、普段よく行くお店の株を持っているとしましょう。「サービスセンスが良いな」「今後伸びそうだ」と思い、その会社の株を買う。こうして個人投資家になるわけですね。ですが、通っているうちに「最近はサービスが雑だな」という印象を持つようになる。そうなると、「業績が落ちるかもしれないからそろそろ売却しよう」という投資判断を下す。こういうこともあり得ます。
そこにプラスして、有価証券報告書を読み込むスキルがあると、なかなか良い投資判断ができるのではないでしょうか。
ただ、投資初心者の方はやはり、個別の株式よりも、プロが運用する投資信託からスタートすることをおすすめします。
「株主優待」がメディアで取り上げられたり話題になることがあります。でも株主優待を受けるためには株式投資が必要で、一定のリスクをとる必要がありますよね。
株主優待はあくまでも「おまけ」だと思ってください。株式投資には、ある程度まとまった金額が必要で、投資信託のように100円から始められるわけではありません。企業の業績が悪化すると、株主優待が廃止されることもあります。まずは企業の業績を見て株価に注力することの方が、優先順位が高いと思います。
「株主優待を狙って株式を購入したのに、株価が下がった」となると、本末転倒ですね。
株式を発行できるのは株式会社だけ
株式がどのような仕組みで作られているのかを整理していきます。株式は、企業が資金調達のために発行する有価証券であると冒頭でお聞きしました。
まず、株式を発行する会社は「株式会社」に限られます。株式会社以外にもいくつか会社の形態があります。
合同会社などがありますね。
現在は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類です。昔は「有限会社」もありましたが、いまは廃止されて新規設立はできません。この中で、株式を発行するのは「株式会社」のみです。
株式会社とそれ以外の会社の主な違いは、「所有と経営の分離」という点です。
「所有と経営の分離」とは、出資者と経営者を分ける仕組みのことです。株式会社の場合、会社を所有するのは株主で、経営するのは経営者です。ただ、株式会社でも、経営者が自分でお金を出して株を買い所有者になっている場合もあります。
株式会社は、会社の意思決定機関として「株主総会」を設置し、定期的に総会を開催します。株主総会で役員の就任を決めるなど、経営上の重要な意思決定をする場となっています。
会社に出資している株主の承認を得ずに、経営者が独断で重要な内容を決めることはできません。
株式会社が、企業の運営資金などの調達目的で発行するのが「株式」ですね。
そうです。株式を持っている人は、金額に差はあっても、その企業へ出資していることになります。企業側としては、株式会社という形態は「株式を発行して、資金調達ができる」というメリットがあります。
「この会社の株式を持ちたい」と株式を買う投資家が増えたら、その分資金調達できるということです。他の資金調達の方法として、銀行からお金を借りる「融資」もありますが、融資は銀行に返済する必要があります。
企業が株式の発行で資金調達をした場合、返済する必要はありません。だからこそ、企業としての価値向上を目指す必要があります。
上場企業の株を買うには?
個人投資家が株式を保有する場合、上場されている株式を買うことになりますよね。
その通りです。企業が発行する株式を証券取引所で売買できます。すべての株式会社が上場しているわけではありません。上場にあたっては、証券取引所の審査などをクリアする必要があります。
上場すると、企業にとっては自社のことを世の中に知ってもらえる機会となり、証券取引所という大きな市場から資金調達ができるようになります。
一方で、あえて「非上場」という選択をする会社もあります。資金調達に問題がなければ上場しない選択も可能ですし、上場するかしないかは、それぞれの企業の経営方針により異なります。
上場というのは、「東京証券取引所に上場されている株式」ということでしょうか。
日本で一番大きい取引所は「東京証券取引所(東証)」です。「TOPIX」というインデックスがありますが、これは「東証株価指数」のことです。ですが、実は、証券取引所は日本に4ヵ所あるんです。
東証以外にもあるんですね。
「東京証券取引所(東証)」「札幌証券取引所(札証)」「名古屋証券取引所(名証)」「福岡証券取引所(福証)」があります。
上場されている株式は、証券会社で購入するのでしょうか。
そうです。株式は証券取引所から直接買うことはできず、証券会社を通じて売買する仕組みです。
株式会社の構造を改めて知ることで、「リスク」の話を思い出しました。
株価変動リスクですね。例えば会社の不祥事で株価が下がったり、特許を取得したら株価が上がるなど、株価は常に値動きします。株を売る人が殺到すると売り傾向になり、市場で株価が下がります。逆に、株を欲しい人が増えると買い注文が増えるので、株価が上がります。
株価の上下は、基本的に業績に連動しますので、会社のレピュテーション(企業に対する社会的な評価)だけが要因ではありませんが。
また、「トランプ関税の中、どの企業の株式を売買するのか」など、政治的な要因でも株式に対する見方が変わります。必ずしも何か一つの理由があるというわけではありません。マクロ視点とミクロ視点がどちらも必要ですね。
第36話のまとめ
- 株式会社が企業として資金調達するために発行する証券のことを株式という
- 会社の形態は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類がある
- 株式会社では、基本的に所有者である株主と経営者が分離している
パーソナリティー:泉田良輔プロフィール
株式会社モニクル
取締役 グループ戦略担当
泉田 良輔 Ryosuke Izumida
慶応義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。2013年3月、株式会社ナビゲータープラットフォーム(現:株式会社モニクルリサーチ)を共同設立し、取締役に就任(現在は代表取締役)。2018年11月、株式会社OneMile Partners(現:株式会社モニクルフィナンシャル)を共同設立し、取締役に就任。2021年10月、ナビゲータープラットフォームとOneMile Partnersの親会社として、株式会社モニクルを設立し、取締役に就任。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。東京科学大学大学院非常勤講師。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程修了。著書に「銀行はこれからどうなるのか」「Google vs トヨタ」「機関投資家だけが知っている『予想』のいらない株式投資法」など。












