金融分野共通#18 新NISA制度を知ろう!③今、新NISA口座ってどれくらいの人が持っている?年代によっては「スイッチング」可否がポイントに 【第26話】
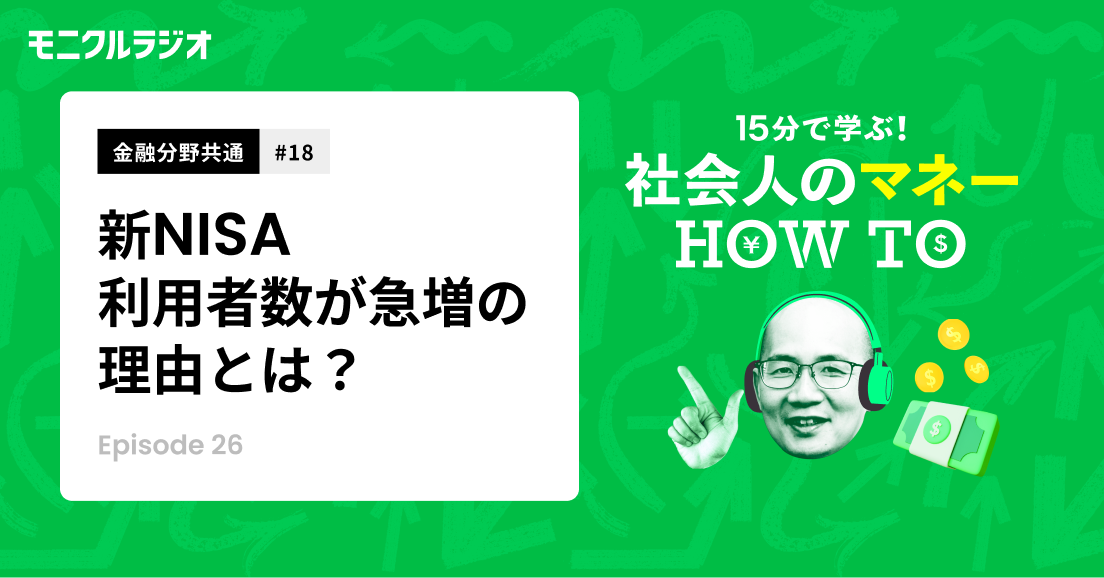
ポッドキャストを聴く(金融分野共通#18 新NISA制度を知ろう!③今、新NISA口座ってどれくらいの人が持っている?年代によっては「スイッチング」可否がポイントに【第26話】)
はじめに
音声メディア『モニクルラジオ』がお届けする金融教育ポッドキャスト「15分で学ぶ!社会人のマネーHOW TO」は、「これだけおさえておけば、お金で大ケガをしない!」をコンセプトに、全50回のプログラムを配信しています。この番組では、学校の金融教育カリキュラムを作る際にも使用されている「金融リテラシー・マップ」にまとめられている項目を踏まえながら、金融知識をひとつずつ学んでいきます。
今回は、第26回の「金融分野共通#18 新NISA制度を知ろう!③今、新NISA口座ってどれくらいの人が持っている?年代によっては「スイッチング」可否がポイントに【第26話】」でお話しした内容を記事としてお届けします。
新NISA口座の開設数が「2560万件」を突破
2024年1月から新NISAがスタートして、利用されている方が増えた印象があります。NISA口座はいま、どれくらいの方が開設しているのでしょうか。
金融庁が発表した「NISA口座の利用状況調査」の速報値によると、2024年12月時点で2560万口座を突破しています。2023年12月末と比べて、約20%も増えているんです。
特に、どの世代にNISAが浸透しているのでしょうか?
口座数は、40代から50代が全体の40%弱を占めていて、もっともボリュームの多い世代です。ですが、2023年12月と2024年9月のデータを比較すると、10代の口座数が2倍になり、20代も27%も増えています。NISAが若年層にも着実に広がっていることが見て取れますね。
投資額の規模も大きくなっていて、2024年だけで20兆円近くも増えたと金融庁が発表しています。
NISAは一人一口座の制度なので、「口座数=開設している人の数」ということですよね。やはり、使いやすい制度になったので開設する方が増えたのでしょうか。
そうですね。日本証券業協会が2024年に実施した「個人投資家の証券投資に関する意識調査(調査結果概要)」という調査結果を見ると、
「大きな資金がなくても、少額から投資が始められることが分かった」
「長期投資や分散投資を意識するようになった」
「預貯金だけではなく、投資を通じた資産形成の必要性を感じるようになった」日本証券業協会「個人投資家の証券投資に関する意識調査 (調査結果概要)」
と、新NISA制度を通じて投資が身近になり、投資の重要性を改めて感じたという方が多いようです。
また、有価証券への投資に興味を持ったきっかけとして、「投資に関する税制優遇制度があることを知ったから」「少額からでも投資を始められることを知ったから」と回答した20代〜30代の割合も多くなっています。
新NISA制度は、投資を始める大きなきっかけになっていますね。個人投資家はこれからも増えていきそうです。
そうですね。だからこそ、金融リテラシーをしっかりと身につけていただきたいですし、モニクルグループとしても、適切な情報を届けていく必要があると考えています。
年代別に見る新NISAの利用目的
先ほどの日本証券業協会の調査結果に、「NISAを何のために利用しているか?」という項目があります。どの項目が上位にあると思いますか?
やはり、「人生の三大資金」の中で、最も大切な「老後資金」でしょうか?
その通りです。「老後の生活資金づくり」がトップで、他には以下のような理由が上位に上がりました。
「老後の生活資金づくり」
「生活費の足し」
「旅行やレジャー資金づくり」
「子や孫へ残す資金づくり」日本証券業協会「個人投資家の証券投資に関する意識調査 (調査結果概要)」
中でも特に、20~30代の回答結果を見ると、
「老後の生活資金づくり」
「生活費の足し」
「子や孫へ残す資金づくり」日本証券業協会「個人投資家の証券投資に関する意識調査 (調査結果概要)」
が上位に上がっています。「住宅購入のための資金づくり」などもありますね。
新NISAをリタイア後に始める場合の注意点
NISA制度は、すべての方におすすめできる投資手法なのでしょうか?
現役世代にとっては、メリットが大きいと思います。私は学生時代に初めて証券口座を開設しましたが、当時、新NISA制度があったら確実に使っていたと思います。
リタイア後の世代については、いかがですか?
その人の資産状況によりますが、一点、大きな注意点があります。現在のNISA制度は「長期の運用」を前提とした設計になっているので、短期売買にはやや不便です。
通常の証券口座であれば「損益通算」(投資などで生じた損失を、他の所得から控除すること)ができますが、NISA口座ではできません。NISAは、投資で利益が出ないとメリットがない制度です。短期売買では損をする回数も多くなり、「普通の特定口座で運用する方が使い勝手が良い」という方もいらっしゃるかもしれません。
退職後、子どもや孫のために資産を増やしたい場合は、資産を取り崩しながら運用を続けていく方が増えます。また、生活費の一部を取り崩しながら、手元にある資産を同時に運用して活用したいというニーズもあります。
そうなると、臨機応変に商品をスイッチしたいケースもあるかと思います。
例えば、Aという投資信託を買ったけれど、Bという商品の方が良いと判断したので買い替えたい、ということですね。
その通りです。ですが、現行のNISA制度では売却した枠が復活するのは1年後になってしまいます。頻繁に商品の入れ替えをしたい場合、「時間のロス」がもったいないですよね。
ある程度資産に余裕がある場合は、通常の口座(課税口座)を開設して、短期目線で運用してみるという方法もあります。
投資信託から個別株へ 新NISAの活用戦略
資産形成中の方も、新NISA制度で運用している資産を売却しながら運用してもいいのでしょうか。
目的が明確であれば、必要に応じて売却しても良いのではないかと思います。新NISA制度のメリットは、いつでも売却できる点にあります。
iDeCoは途中で売却しても、原則として資金を取り出すことはできません。そこが新NISA制度とは違う点ですね。
iDeCoで運用する資産は、60歳まで取り出せないですよね。
iDeCoは、着実に老後資金を作れるように設計されている制度ですが、新NISAは、よりフレキシブルに資産形成ができるところが魅力です。
長期目線も短期目線も持ちながら、自分でコントロールできるのですね。
はい。特に「つみたて投資枠」は、投資信託で資産形成するので、これから投資に慣れたいという初心者の方も始めやすいでしょう。
投資信託はプロが運用してくれて、株式や債券、REITなどの幅広い金融商品に投資ができますし、国内、先進国、新興国など、対象エリアも幅広いです。
自分で株式を購入すると、一社一社動きを追う必要が出てきますよね。
そうですね。「投資信託で動きを見ながら、気になる株がでてきたら成長投資枠で買う」という流れがいいのではないかと思います。
もちろん、新NISA制度にもさまざまなリスクはありますが、投資を始めるには、いい制度ができたという印象です。
第26話のまとめ
- 新NISA制度は、現役世代にはメリットが大きい。一方で、リタイア後はスイッチングの時間ロスがもったいない場合も
- 新NISA制度は、長期運用を前提に設計されているが、途中で売却できるフレキシブルさも魅力
- 投資信託はプロが運用してくれる。新NISAの「つみたて投資枠」は、投資初心者には使いやすい制度
パーソナリティー:泉田良輔プロフィール
株式会社モニクル
取締役 グループ戦略担当
泉田 良輔 Ryosuke Izumida
慶応義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。2013年3月、株式会社ナビゲータープラットフォーム(現:株式会社モニクルリサーチ)を共同設立し、取締役に就任(現在は代表取締役)。2018年11月、株式会社OneMile Partners(現:株式会社モニクルフィナンシャル)を共同設立し、取締役に就任。2021年10月、ナビゲータープラットフォームとOneMile Partnersの親会社として、株式会社モニクルを設立し、取締役に就任。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。東京科学大学大学院非常勤講師。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程修了。著書に「銀行はこれからどうなるのか」「Google vs トヨタ」「機関投資家だけが知っている『予想』のいらない株式投資法」など。












