金融分野共通#13 政策金利が変動すると、株価や債券価格はどうなる?長期金利、短期金利の概念を知ろう 【第21話】
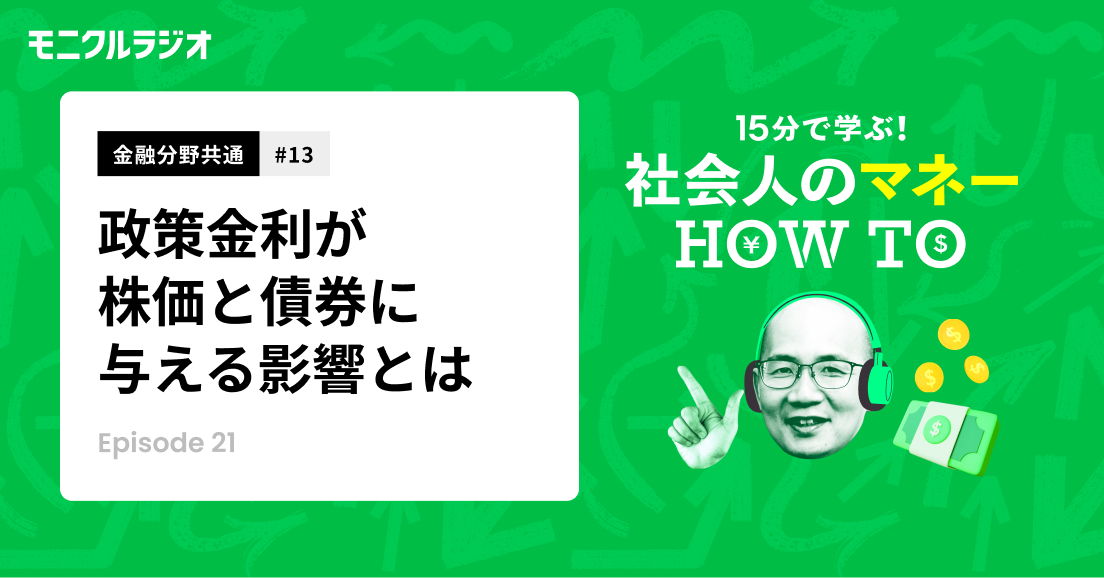
ポッドキャストを聴く(金融分野共通#13 政策金利が変動すると、株価や債券価格はどうなる?長期金利、短期金利の概念を知ろう【第21話】)
はじめに
音声メディア『モニクルラジオ』がお届けする金融教育ポッドキャスト「15分で学ぶ!社会人のマネーHOW TO」は、「これだけおさえておけば、お金で大ケガをしない!」をコンセプトに、全50回のプログラムを配信しています。この番組では、学校の金融教育カリキュラムを作る際にも使用されている「金融リテラシー・マップ」にまとめられている項目を踏まえながら、金融知識をひとつずつ学んでいきます。
今回は、第21回の「金融分野共通#13 政策金利が変動すると、株価や債券価格はどうなる?長期金利、短期金利の概念を知ろう【第21話】」でお話しした内容を記事としてお届けします。
日銀の「政策金利」について解説
今日のテーマは「日本銀行の『政策金利』について」です。
前回、日本銀行は「銀行の銀行」だという話をしました。今回は日銀が決める「政策金利」について、解説していきます。
「それぞれの銀行が預かっている預金から、一定の割合の金額を日本銀行に預け入れる」という制度でしたね。
その通りです。「準備預金制度」とは、各銀行が、預金などの残高に応じて一定の比率以上の金額を、日銀に預け入れる制度です。
民間の銀行が日銀に預けている預金のうち、最低限預けなければならない額(法定準備預金)を超える部分については、日本銀行から利子が支払われます。この超過した部分を「超過準備」と呼び、ここに適用される金利は政策金利と同じ水準です。
例えば、A銀行が1000億円の預金を保有し、そのうちの10億円が法定準備預金だとします。A銀行が30億円を日銀に預けた場合、超過分の20億円に対して利子が付く、ということでしょうか。
その通りです。ポイントになるのは、法律で預ける義務がある「所要準備」には利子が付かず、それを超えた「超過準備」にのみ利子が付く、という点です。
そうなると、民間の銀行は、自身が預かっている預金をどのように運用すると思いますか?
政策金利が上昇すれば、日銀への預け入れを増やすのではないでしょうか。日銀に預けておくだけで、利息によって資金が増えるわけですから。
そうですね。通常は民間の銀行は、皆さんから預かった預金を、企業や個人などに金利を付けて貸し出し、利益を得ています。
ですが、日銀に預け入れただけで収益が見込めるなら、銀行は企業や個人への貸し出しに消極的になる可能性がありますよね。
確かに、積極的に貸し出し先を探すより、日銀口座に置いておく方が効率的です。貸し倒れのリスクもありませんよね。
政策金利が上昇すると、ビジネス的な判断として、「日銀に預けるだけで〇〇%の利子が得られるのだから、リスクを冒して民間に貸し出す意義は薄い」と考えますよね。
同時に、政策金利が上がっているわけですから、住宅ローンの金利や、企業・個人事業主への融資金利も上昇していきます。銀行があえてリスクを取って貸し出す以上、それに見合うリターンを求めるからです。
政策金利は預貯金にどう影響する?
政策金利が上昇すると、私たちが銀行に預けている預貯金の金利も上昇しますか?
その傾向はあります。銀行にとって多くの預金を集めることは、事業を拡大していく上で必要ですし、また貸し出しのための資金調達手段でもあります。
政策金利が変動すると、金融商品にはどのような影響があるのでしょうか。
金融商品やローンの利息などで注目されるのは「長期金利」です。一方で、日本銀行が決定する政策金利は、「短期金利」に分類されます。
「短期金利」と「長期金利」。これまでにも登場した言葉ですが、改めて違いを教えてください。
金融の世界では、一般的には、1年より長ければ「長期」、1年未満であれば「短期」です。
日本銀行は年に8回、「金融政策決定会合」という会議を開き、今後の金融政策について議論します。政策金利も、この会合で決定されます
この会合で決定された政策金利が、ニュースで報道されるわけですね。
はい。短期金利である政策金利は、この会合で具体的な数値目標が定められますが、長期金利は、政策金利の影響を受けつつも、その他のさまざまな要因によって決まっていくものです。
例えば、世の中の長期的な資金の需要と供給のバランスや、将来の物価変動に対する予想によって左右されます。
長期的な資金の需要と供給のバランスとは、「1年以上の期間で、銀行から資金を借りたいと考える企業数と、借りたい金額がどの程度か」ということですか?
はい、その通りです。長期金利の代表的な指標となるのが「10年物の日本国債の利回り」です。住宅ローンの金利も、この10年物国債の利回りに影響を受けます。住宅購入を検討している方は確認しておくと良いでしょう。
金利が動くと金融商品の価格も変わる
金融資産の価格変動に直接的に関わるのは、長期金利なのでしょうか。例えば、債券の場合はどのような影響が出ますか?
金利が上昇すると、一般的に債券の価格は下落する傾向にあります。ただし、これは既に発行されている債券の価格についていえることです。
例えば、利率2%の固定利付債券を保有しているとします。その後、新たに発行される同種の債券の利率が3%になった場合、手持ちの利率2%の債券は魅力が薄れますよね。
これは、将来受け取れる利子の額が固定されているため、より高い利回りを提供する新しい投資機会と比較して不利になるためです。結果として、この利率2%の債券の現在価値が下がり、市場で取引される際の価格も下落する、という仕組みです。
金融の世界には、「割引現在価値」という考え方があります。これは、将来得られる収入を、現在の価値に割り引いて評価する計算方法です。この考え方に基づくと、金利が上昇すると割引率が上昇するため、結果として債券価値が下落することになります。
それでは、株価についてはどうでしょうか?
政策金利が上昇すると長期金利も上昇する傾向があるため、株価も債券同様、下がる可能性があります。先ほどの債券価格の考え方と同じで、企業が将来生み出すと期待される利益(フリーキャッシュフロー)の割引現在価値が、金利の上昇によって低下するためです。
とはいえ、金利と金融商品の価格変動については、あくまで理論上の傾向であるという点に注意が必要です。債券も株式も、金利だけでなく、海外の資産であれば為替レートの変動など、さまざまな要因の影響を受けます。
一般的な傾向としてこうした考え方を理解しておくと、「政策金利が上昇した。今後どのようなことが起こり得るか?」ということを予測しやすくなるでしょう。
投資信託についても、債券や株式と同様のことがいえるのでしょうか?
どのような商品を組み合わせている投資信託かにもよりますが、一般的に金利が上昇すれば、債券価格や株価は短期的には下落する傾向にあります。結果として、そうした資産を組み入れている投資信託の価格も下落する可能性がある、と理解して良いでしょう。
ですが、金利が上がっているときこそ、株を買うチャンスともいえます。金利が上昇すると株価が下がりやすくなるため、割安になったと捉えて「買い時」と考えることもできます。
第21話のまとめ
- 金融の文脈での長期・短期とは、1年を超えるかどうか。1年未満は短期、1年を超えると長期
- 日本銀行が発表する政策金利は、短期金利であり、長期金利にも影響を及ぼす
- 長期金利の代表的な指標となるのが、「10年物の日本国債」の利回り
- 金利が上がると債券や株価は下がる傾向にあるが、あくまでも理論上であることに注意。ただし、この関係性を知っておくと資産形成の判断材料として有用である
パーソナリティー:泉田良輔プロフィール
株式会社モニクル
取締役 グループ戦略担当
泉田 良輔 Ryosuke Izumida
慶応義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。2013年3月、株式会社ナビゲータープラットフォーム(現:株式会社モニクルリサーチ)を共同設立し、取締役に就任(現在は代表取締役)。2018年11月、株式会社OneMile Partners(現:株式会社モニクルフィナンシャル)を共同設立し、取締役に就任。2021年10月、ナビゲータープラットフォームとOneMile Partnersの親会社として、株式会社モニクルを設立し、取締役に就任。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。東京科学大学大学院非常勤講師。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程修了。著書に「銀行はこれからどうなるのか」「Google vs トヨタ」「機関投資家だけが知っている『予想』のいらない株式投資法」など。












