金融分野共通#9 4月3日は、資産形成を考える日!インフレーションの時は、投資?預貯金?資産形成、何から始める?【第17話】
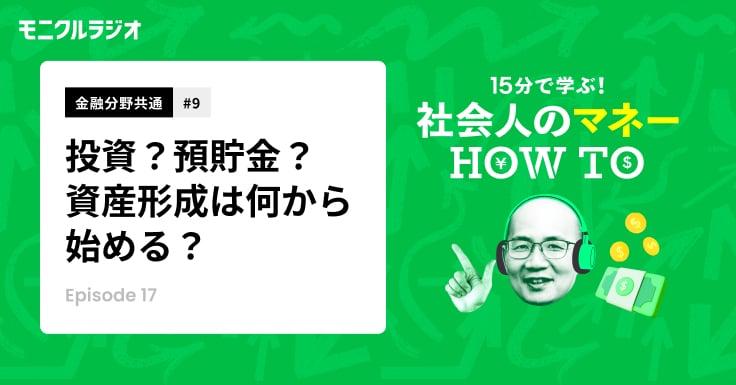
ポッドキャストを聴く(金融分野共通#9 4月3日は、資産形成を考える日!インフレーションの時は、投資?預貯金?資産形成、何から始める?【第17話】)
はじめに
音声メディア『モニクルラジオ』がお届けする金融教育ポッドキャスト「15分で学ぶ!社会人のマネーHOW TO」は、「これだけおさえておけば、お金で大ケガをしない!」をコンセプトに、全50回のプログラムを配信しています。この番組では、学校の金融教育カリキュラムを作る際にも使用されている「金融リテラシー・マップ」にまとめられている項目を踏まえながら、金融知識をひとつずつ学んでいきます。
今回は、第17回の「4月3日は、資産形成を考える日!インフレーションの時は、投資?預貯金?資産形成、何から始める?」でお話しした内容を記事としてお届けします。
預貯金だけで大丈夫?お金との向き合い方
今日は、資産形成全般についてお話を伺っていきます。投資にはリスクがつきものですし、何から始めたらいいのか分からない方も多いと思います。結局は預貯金が一番安心だと思えるのですが、いかがでしょうか?
僕の考えでは、預貯金だけに頼る方が、むしろリスクが高いと思います。
年齢や資産状況によって、資産運用のスタイルやリスクの取り方は異なりますが、特に若い世代ほど預貯金だけではもったいないと感じますね。
もちろん投資をしなくても、人生の三大資金(住宅、教育、老後)を用意できる場合もあります。たとえば給与水準が高く、毎月一定額を貯金し続けることができる場合です。
また、長期で資金を準備しようとすることも大事なのですが、人生においては思わぬ事故や出来事に直面することもあります。資産形成の途中でも、家族のために、万が一を想定した保険に入っておくことも選択肢の一つです。
経済は日本国内だけで動いているわけではなく、世界と連動しています。為替や世界情勢の影響で日本円の価値も一定ではないですし、老後の物価もどうなるか分かりません。
「インフレーション」と「デフレーション」という言葉は聞いたことがありますよね。
インフレは物価が上がる、デフレは物価が下がるという意味ですね。
そうです。例えば、インフレになると100円で買えていたパンが200円になったり、デフレになると100円のパンが50円になったりします。最近だと、お米の値段がずいぶん上昇したことは皆さんが実感していることではないでしょうか。
100万円の預貯金をしていたとして、パンが200円になると同じパンの個数を購入するという前提に立つと、預貯金の価値は50万円、デフレの場合は200万円の価値になります。
物価の変動に合わせて、現金の価値も増えたり減ったりしてしまうんですね。
現在は「円安」が進んでいます。「円安ドル高」という状態で、ドルと比べると円の価値が相対的に下がっている状態です。
このような状況では、現金のまま寝かせておくよりも、投資などで資産運用して増やす方が良いのではないでしょうか。
では、デフレの場合には、投資ではなく預貯金をした方が良いのでしょうか?
日本で生活をするという前提においては、デフレ時は現金が一番強いです。ただ、日本はデフレでも、海外ではインフレだったので、投資機会は海外にあるともいえます。
経済動向を読みながら判断するのが大事だということですね。
そうですね。投資などの手段を使って資産運用をするかしないかは自由なので、「投資は一切しない」という選択も、もちろん問題はありません。
ただ、「知らないから何もしない」のではなく、「知った上で何もしないと判断をする」のが良いのではないかと思います。
資産形成はなぜ必要?若い世代こそ考えておきたい
「資産形成をしたいが、何から始めたらいいのか分からない」という方もいらっしゃいます。このような場合はどうしたらいいでしょう?
まずは「なぜ資産形成をする必要があるのか」、つまりライフプランニング(人生設計)を考えてみると良いでしょう。
「いつかこんなことをしたい」とか、「何をしたいか分からないけれど、将来に向けてお金は持っておきたい」などですね。人生には意外とお金がかかります。
学生の場合、一人暮らしの大学生の方は意識しているかもしれませんが、「学費はいくら」「食費はいくら」など、自分に関するお金が日々どれくらいかかっているのかを考えるところから始めてもいいかもしれませんね。
一人暮らしをすると、家賃や生活費を意識する機会も多そうです。
ただ、焦って投資を始めたり、何も分からない状態で始めるのは危ないと思います。金融トラブルに巻き込まれる恐れもあります。
「絶対に儲かる」という詐欺広告や、著名人を使った投資を勧誘するニセ広告。最近だと簡単な仕事で法外な報酬をもらえる「闇バイト」などはとても危険です。
いまは問題になっていなくても、「これは危ないかもしれない」というアラートが、自分の中で上がるようにしておくことが大切です。原則として、楽してお金を得られることはないですから。
「資産形成を始めるのが怖い。失敗するくらいなら何もしない方がいいのではないか」、こう考えてしまう場合はどうしたらいいですか?
まず、資産形成をするかしないかでいうと、しなければならないものではありません。自分で始めるかどうかを決めることができます。
2024年は「新NISA」がブームでしたが、これも立派な投資なので「失敗してお金がなくなった」となっても、誰も責任はとってくれませんよね。
確かにそうですね。そこが投資に踏み切れない怖さかもしれません。
一方で、「老後資金が足りない」というのも、お金に関するリスクになります。また他にも「想定していない病気やケガで、保険診療でカバーできない高額な医療費がかかるようになった」、「病気やけがで働けなくなってしまった」というリスクも考えられます。
人生のトラブルは、事前に予測して防げることばかりではありません。でも「お金」については、考えて行動できることもあります。
「何もしないほうがリスクだ」ということですね。
そうです。投資は複利(増えたお金にも金利がつくので、効率よく資産が増えていくこと)の効果も考えると、早く始めるのに越したことはありません。若いうちなら、仮に投資で失敗しても挽回できるので、リスクが取れます。
投資でうまくいくと「FIRE」(経済的自立と早期リタイア)ができたり、人生の選択肢も広がる可能性もあります。
保険も含めて「備える」視点を
資産形成だけではなく、保険についても考える必要がありますか?
そうですね。民間保険の場合は、未加入のまま年を重ねていくと、いざ必要になったときに加入ができないケースがあります。申し込みには健康診断の結果の提出を求められることがあり、審査に通らないこともあります。
保険会社では、保険に未加入の方を「無保険者」と呼びますが、年齢とともに健康リスクが高まると、未加入の状態に不安を感じることもあるでしょう。一度病気になると、新たな契約ができなかったり、保険料が大幅に上がってしまうこともあります。
保険商品自体もどんどんアップデートされていきます。医療保険は特にその傾向があります。医療の内容は日々変化していますし、入院可能な期間も病院経営の状況と不可分です。若い頃に加入した保険が、ずっと最適であるというわけではないので、定期的な見直しも大切ですね。
保険については、若い頃はなかなか必要性を感じにくいかもしれません。
日本は社会保障が充実しているので、過剰に準備する必要はありません。ただ、この制度は保険料をこれまで通り徴収できるという加入者同士で支えあうという前提に立っているので、この先も同じ基準で保障されるとは限りません。少子高齢化が影響してきます。実際に、高額療養費制度については現在議論されています。
保険については、身近なところだと損害保険の「自転車保険」などもあります。これは、加入が義務になっている都道府県もあります。
自転車に乗っているときに、万が一誰かにケガをさせてしまったときの賠償金などに対する保険でしょうか。
そうです。あとは、自分自身のケガへの賠償もあるので、自転車に乗る方は一度調べてみてください。
初心者こそ投資のプロに相談を
先ほど「投資をしないこともお金に関するリスクである」というお話がありましたが、読者の中には「泉田さんは、投資の専門家だからできるのでは」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、投資判断においては、専門的なスキルが求められる状況もあります。
ですが、今の環境では、投資は決してプロだけのものではありません。例えば、長期的に積み立てていく「分散型の積立投資」であれば、専門性はあまり関係ないと思います。
投資というと、チャートを見ながら頻繁に株式を売買をするようなイメージがあるかもしれませんが、そうした複雑なことを行う必要はありません。
初心者が資産形成を始めたいと思ったら、何から始めるのが良いでしょうか。
自分で始めたいのであれば、まずは資産形成の原則を押さえた上で、実際に少額から始めてみると自分で感覚がわかると思います。
最近は、つみたてNISAやiDeCo、2024年から始まった新NISAなどで運用を始めた方が多く、SNSを見ても詳しい方が増えた印象があります。
自分でつみたて投資を始めてみて、「さらに細かくやりたい。こだわりたい」という方は、自分で勉強を進めるか、プロに相談することをおすすめします。もちろん、最初からプロに相談してもいいですし。
プロにはどちらで相談できるのでしょうか?
銀行や証券会社のファイナンシャルアドバイザーや、IFAという独立系ファイナンシャルアドバイザーが対応してくれます。
新NISAも相談できますか?
相談できます。むしろ、いまは新NISAの相談が多いのではないでしょうか。
初心者の方が新NISAを使いやすいだろうなと思うのは、少額から投資を経験できるところです。いろいろな商品もありますし、選びながら勉強もできます。
つみたて投資も100円からできるところもあります。100円では数字の上下や利率も大きくないので「投資している」という実感はあまりないかもしれません。でも、無理ない金額で始められるのがポイントだと思います。
新NISAは売却益などに税金がかからないだけではなく、少額からできるという安心感もあるんですね。
新NISAのつみたて投資枠では、基本的に「投資信託」を買うことになります。投資信託はファンドマネージャーというプロが運用してくれます。「どの商品を、どういう配分で、どう買うか」が不安な方は、相談されると良いのではないでしょうか。
プロが運用してくれるのは心強いですね。
「分からないことはプロに相談する」、これが一番手っ取り早い方法です。僕も税金や医療に関してはプロに相談しますので、資産形成については資産形成のプロに相談することをおすすめします。知識をインプットしながら、自分を過信せず、必要な時にはプロに頼る。このスタンスが大切だと思います。
必ずしも資産を思い通りに増やせるわけではないですが、「複利」の効果や、積立投資は時間をかけるほど有効です。若いうちは、将来必要なお金や人生の紆余曲折をイメージしづらいですが、なんといっても時間を味方にできます。そういう観点で資産形成を考えてみるのも、何かヒントになるかもしれません。
パーソナリティー:泉田良輔プロフィール
株式会社モニクル
取締役 グループ戦略担当
泉田 良輔 Ryosuke Izumida
慶応義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。2013年3月、株式会社ナビゲータープラットフォーム(現:株式会社モニクルリサーチ)を共同設立し、取締役に就任(現在は代表取締役)。2018年11月、株式会社OneMile Partners(現:株式会社モニクルフィナンシャル)を共同設立し、取締役に就任。2021年10月、ナビゲータープラットフォームとOneMile Partnersの親会社として、株式会社モニクルを設立し、取締役に就任。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。東京科学大学大学院非常勤講師。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程修了。著書に「銀行はこれからどうなるのか」「Google vs トヨタ」「機関投資家だけが知っている『予想』のいらない株式投資法」など。












