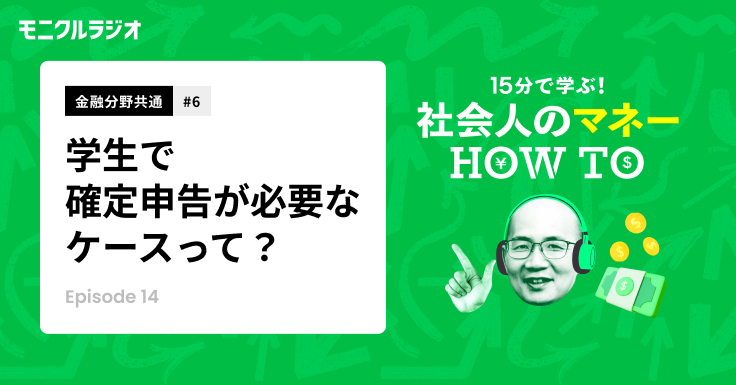
ポッドキャストを聴く(金融分野共通#6 学生アルバイトも確定申告必要?金融所得課税って何?所得の壁について知る!【第14話】)
はじめに
音声メディア『モニクルラジオ』がお届けする金融教育ポッドキャスト「15分で学ぶ!社会人のマネーHOW TO」は、「これだけおさえておけば、お金で大ケガをしない!」をコンセプトに、全50回のプログラムを配信しています。この番組では、学校の金融教育カリキュラムを作る際にも使用されている「金融リテラシー・マップ」にまとめられている項目を踏まえながら、金融知識をひとつずつ学んでいきます。
今回は、第14回の「学生アルバイトも確定申告必要?金融所得課税って何?所得の壁について知る!」でお話した内容を記事としてお届けします。
学生アルバイトで確定申告が必要なケースとは
今日のテーマは「学生の確定申告について」です。学生の方にとっては、確定申告と言ってもピンと来ないかもしれませんが、学生でアルバイトをしている場合、確定申告は必要なのでしょうか?
前提として、学生に限らず、雇用元が1社のみで年末調整をしてもらえる場合は、確定申告は不要です。
アルバイトやパートタイムで、複数の仕事を掛け持ちしている場合はどうなりますか?
例えば、A社とB社でアルバイトをしていて、A社の給与所得のほうが多い場合、年末調整はA社で行い、B社の給与所得については個人で確定申告をするのが一般的です
年末調整を2社それぞれで行うことはできないのですね。
はい。扶養控除などの控除が重複し、正しい数値を把握できなくなるため、2社それぞれで行うことはできません。金額が多いほうの給与を「主たる給与」、少ないほうを「従たる給与」といいますが、年末調整は、「主たる給与」をもらった会社でのみ行います。
この仕組みは会社員の副業にも当てはまります。副業の場合も、「2か所以上から給与所得がある」場合に該当するため、「主たる給与」をもらった会社でのみ、年末調整を行います。
転職して会社が変わった場合はどうなるのでしょうか?
年度途中で転職した場合、前職の源泉徴収票を現在の会社に提出すると、まとめて年末調整をしてもらえます。
ですが、退職後に年内に再就職せず、年末調整を行わなかった場合は、確定申告をした方がよいでしょう。納めすぎた所得税などが還付される可能性があります。
2025年の税制改正、控除額はどう変わる?
「103万円の壁がなくなった」というニュースを聞きました。これも控除に関わる話でしょうか。
2025年度の税制改正によって、年収200万円以下の人に適用される基礎控除は95万円、給与所得控除の最低保障額が65万円となりました。控除額の合計額は、95万円と65万円を足した160万円まで引き上げられました。
よって、課税される最低ラインの年収が160万円になり、これまで103万円だった年収の壁は2025年度から160万円に引き上げられた形になります。
(※収録では決定前の内容を話題にしています。)
2025年の所得から適用されるのですね。
はい。この変更は、「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」にも影響を及ぼします。世帯全体の納税額を考える際には、家族構成や控除額を考慮する必要があります。
社会保険の壁は収入のボーダーラインに注意
所得税とは別に、「社会保険の壁」もありますが、詳しく教えてください。
例えば、会社の規模によっては「106万円の壁」が適用され、一定の収入を超えると健康保険や厚生年金保険の加入義務が発生します。また、「130万円の壁」を超えると扶養を外れ、自分で社会保険に加入する必要が出てきます。結果として、手取りが減ることになるため注意が必要です。
収入が一定額を超えると、社会保険料の負担が発生するのですね。
そうです。現在、これらの壁を撤廃する案も議論されていますが、今後の動向に注目が必要です。
「扶養控除」についても教えてください。
扶養控除は、お子さんやご高齢の親御さんなど扶養親族がいる場合に適用される控除です。「特定扶養親族」というカテゴリがあり、こちらは19歳以上23歳未満の扶養家族が該当します。大学生は、この「特定扶養親族」にあたることが多いですね。
2025年度の税制改正によって、大学生がアルバイトで給与収入を得ている場合、親の扶養控除枠に収まる上限が150万円に引き上げられました。
子の年収の上限を150万円に引き上げ、それまでは控除が受けられるようになります。
123万円を超えたあとは「特定親族特別控除」となり、150万円を超えた後も、控除額を段階的に減らす仕組みを導入し、収入が増えたにも関わらず世帯としての手取りが減ることはないようにします。
ただし、「社会保険の壁」は依然として残っています。130万円を超えると扶養から外れ、手取りが減る可能性があります。
年収150万円までは扶養枠の控除内に収まるが、130万円を超えると社会保険への加入義務が発生するのですね。
その通りです。また、住民税についても考慮する必要があります。住民税は自治体ごとに異なりますが、一般的には年収100万円が課税のボーダーラインになります。
税率差が生む「1億円の壁」の問題
金融商品を保有すると、税金が発生することもあるのでしょうか?
はい。「金融所得課税」というものがあります。
以前、所得は10種類あると聞きましたが、その中に「金融所得」という分類はなかったように思います。
そうですね。金融所得とは、「利子所得」「配当所得」「株式の譲渡所得」など、金融商品から得た所得の総称です。それらにかかる税金が「金融所得課税」と呼ばれます。
金融所得がある場合も、確定申告が必要なのでしょうか?
金融機関が源泉徴収する場合は、確定申告が不要なケースもあります。ただし、「配当控除」や「損益通算」を活用すれば税負担を減らせる可能性があるため、確定申告を検討するとよいでしょう。
なお、FX(外国為替証拠金取引)は、「先物取引に関する雑所得」として扱われ、副業収入などと合わせて20万円を超える場合には、確定申告が必要です。
FXの収入も、場合によっては確定申告が必要になるのですね。
そうです。ただし、金融所得課税の仕組みは複雑で、課税方法には「総合課税」「申告分離課税」「源泉分離課税」などの種類があります。自分の状況に合った方法を選ぶためにも、税理士に相談するのがよいでしょう。
「金融所得課税」の税率は決まっているのでしょうか?
金融所得課税は、一律「20.315%(所得税+住民税+復興特別所得税)」です。
ただ、現在「1億円の壁」として問題視されている点があります。所得税は累進課税制度を採用しており、一般的な給与所得では課税所得が4000万円を超えると最大55%の税率が適用されます。
ですが、金融所得課税は一律約20%のため、高所得者ほど税負担が軽くなってしまうのです。この不均衡が、今後の税制改正の議論の対象となっています。
税制度は社会情勢に応じて頻繁に改正されます。最新情報を確認しながら、適切に対応できるようにしましょう。
第14話のまとめ
- 学生アルバイトも、収入しだいで確定申告が必要
- 「103万円の壁」は2025年度の税制改正で「160万円」に見直し
- 住民税のボーダーラインは100万円
- 社会保険料の壁(106万円と130万円)は引き続き注意が必要
- 金融所得課税は、一律約20%。「1億円の壁」問題が議論中
パーソナリティー:泉田良輔プロフィール
株式会社モニクル
取締役 グループ戦略担当
泉田 良輔 Ryosuke Izumida
慶応義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。2013年3月、株式会社ナビゲータープラットフォーム(現:株式会社モニクルリサーチ)を共同設立し、取締役に就任(現在は代表取締役)。2018年11月、株式会社OneMile Partners(現:株式会社モニクルフィナンシャル)を共同設立し、取締役に就任。2021年10月、ナビゲータープラットフォームとOneMile Partnersの親会社として、株式会社モニクルを設立し、取締役に就任。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。東京科学大学大学院非常勤講師。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程修了。著書に「銀行はこれからどうなるのか」「Google vs トヨタ」「機関投資家だけが知っている『予想』のいらない株式投資法」など。












