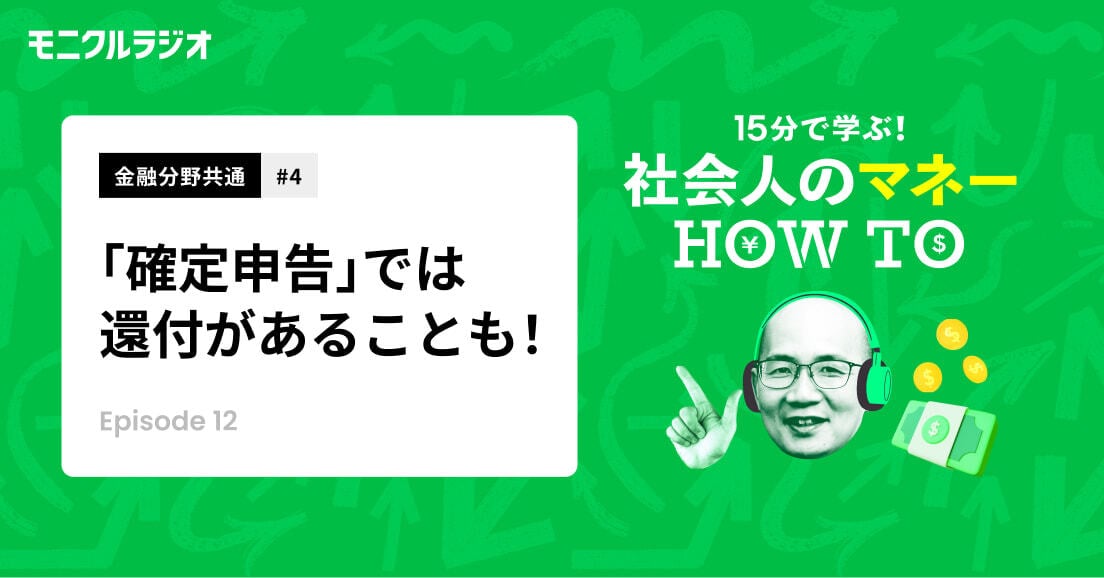
ポッドキャストを聴く(金融分野共通#4 確定申告には、納税と還付の両面あり!年末調整をしていても、必要なケースって? 【第12話】)
はじめに
音声メディア『モニクルラジオ』がお届けする金融教育ポッドキャスト「15分で学ぶ!社会人のマネーHOW TO」は、「これだけおさえておけば、お金で大ケガをしない!」をコンセプトに、全50回のプログラムを配信しています。この番組では、学校の金融教育カリキュラムを作る際にも使用されている「金融リテラシー・マップ」にまとめられている項目を踏まえながら、金融知識をひとつずつ学んでいきます。
今回は、第12回の「確定申告には、納税と還付の両面あり!年末調整をしていても、必要なケースって?」でお話した内容を記事としてお届けします。
3月はお金にまつわるイベントが盛りだくさん
確定申告は毎年2月から3月にかけて行われますが、3月にはお金に関するイベントがいくつか開催されますね。
大きなものとしては、「グローバルマネーウィーク」というイベントがあります。OECD(経済協力開発機構)の「金融教育に関する国際ネットワーク」が主催する国際的な啓発活動で、子どもや若者への金融教育・金融包摂の推進を目的としています。今年(2025年)は3月17日から23日までの一週間、世界各国でイベントが開催される予定です。
日本では、3月1日から31日までを開催期間としており、金融庁や金融経済教育推進機構(J-FLEC)などが参加しています。今年はモニクルも、このポッドキャストを通じて参加しています。(プレスリリース)
確定申告とは?基本から解説
さて、今日のテーマは「確定申告」です。
この番組は、主に学生の方や新社会人の方向けにお届けしています。そこで、今回は「確定申告とは何か?」という基本的な部分から説明しようと思います。
まず正確な情報を得るために、一次情報となる国税庁のホームページを見てみましょう。国税庁のホームページでは、所得税の確定申告について以下のように説明されています。
「毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。」
学生や会社員でも確定申告が必要な場合がある
泉田さんは、いままでに確定申告をされたことはありますか?
僕は大学生の時に雑誌に寄稿して原稿料をもらい、その時に初めて確定申告をしました。その後、源泉徴収された税金が戻ってきました。
学生でも確定申告をする場合があるんですね。では、確定申告が必要なのはどのような方なのでしょうか?
確定申告の対象となるのは、主に個人事業主の方です。基礎控除額は48万円なので、「事業収入が48万円以上ある方」が対象となります。ただし、青色申告等の制度を活用すると、控除額が変わる場合があります。
また、給与所得のある会社員や公務員の方で年末調整をしていても、確定申告が必要なケースがあります。給与以外の所得(副業)が20万円を超えたときや、医療費控除を受ける場合などです。
確定申告は、いつ手続きをしたらよいのでしょうか。
確定申告の手続き期間は、基本的には2月16日から3月15日の間です。ただし、年度によって日程が前後することがあるため、事前に国税庁のホームページで確認することをおすすめします。
先ほど、確定申告をしたら払いすぎた税金が戻ってきたというお話がありましたが、それについても詳しく教えてください。
多くの方は、確定申告というと「税金を納める」イメージを持っているかもしれません。しかし、実際には払いすぎた所得税が戻ってくるケースもあります。このような手続きを「還付申告」といいます。
国の制度として、確定申告(納税)は「義務」ですが、還付申告は「任意」となっているため、手続きを忘れてしまう方もいるかもしれません。還付申告は5年前までさかのぼって申請できるので、過去の申告漏れがないかチェックしてみるとよいでしょう。
例えば、年末調整し忘れた保険控除や、医療保険控除、初年度の住宅ローン控除は、確定申告が必要です。なお、還付申請は通常の確定申告と異なり、1年中受け付けていることも覚えておきましょう。

税金の仕組みとその変遷
そもそも、確定申告とはどのような仕組みなのでしょうか。
確定申告は、納税者が自分の所得を税務署に申告する制度です。日本の所得税は「申告納税方式」といって、納税者が申告した内容をもとに課税されます。一方、住民税は「賦課(ふか)課税方式」が採用されており、国や自治体が決定した税額が通知される仕組みになっています。
この仕組みはいつから導入されたのでしょうか?
所得税が「申告納税方式」になったのは、戦後です。現在の憲法が整備されたタイミングで、いまの税制度の大枠が決まりました。
税金の仕組みは歴史とともに変化しています。例えば、消費税が導入されたのは1989年で、当初は3%でしたが、現在は10%に引き上げられています。社会情勢の変化に合わせて、税率も変動しています。
消費税は、日々実感のある税金ですね。
ちなみに、消費税の使い道は法律で定められており、「年金」「医療」「介護」「少子化対策」などの社会保障に充てられています。
また、現在の日本の税収では消費税の割合が大きくなっていますが、明治時代には「酒税」が最大の財源だった時期もありました。税金の種類や比重は、時代とともに変わってきているのです。

税金の歴史についても調べたくなりましたね。
今回は、確定申告という個人の作業から始まり、国や自治体の財源や税の歴史といった、より広い視点へと話を広げる回となりました。
第12話のまとめ
- 確定申告は所得税を確定させる手続きで、基本的に2月16日~3月15日に実施される。(※日程は年度により前後する場合がある)
- 確定申告には、税金を納める「納税」と、払いすぎた税金が戻る「還付」の2つがある。還付は5年前までさかのぼって申請可能なため、過去の控除漏れがないか確認するとよい。
- 税金は国や自治体の財源となっており、社会保障や公共サービスに使われている。
パーソナリティー:泉田良輔プロフィール
株式会社モニクル
取締役 グループ戦略担当
泉田 良輔 Ryosuke Izumida
慶応義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。2013年3月、株式会社ナビゲータープラットフォーム(現:株式会社モニクルリサーチ)を共同設立し、取締役に就任(現在は代表取締役)。2018年11月、株式会社OneMile Partners(現:株式会社モニクルフィナンシャル)を共同設立し、取締役に就任。2021年10月、ナビゲータープラットフォームとOneMile Partnersの親会社として、株式会社モニクルを設立し、取締役に就任。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。東京科学大学大学院非常勤講師。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程修了。著書に「銀行はこれからどうなるのか」「Google vs トヨタ」「機関投資家だけが知っている『予想』のいらない株式投資法」など。













