家計管理 #2 給与明細には情報がたくさん!所得税って、どうやって決まる? 【第6話】
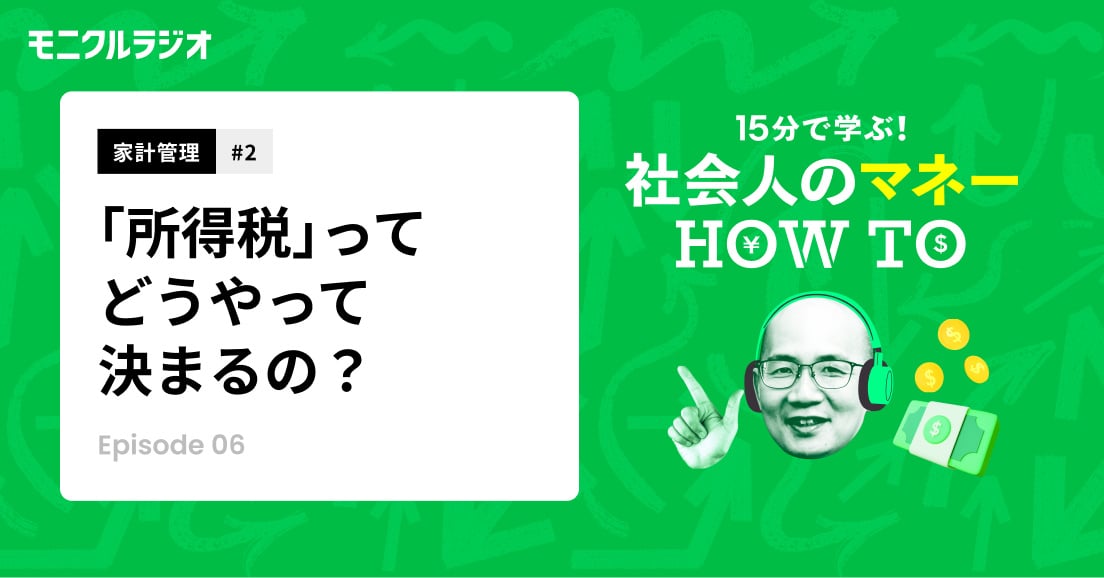
ポッドキャストを聴く(家計管理 #2 給与明細には情報がたくさん!所得税って、どうやって決まる? 【第6話】)
はじめに
音声メディア『モニクルラジオ』がお届けする金融教育ポッドキャスト「15分で学ぶ!社会人のマネーHOW TO」は、「これだけおさえておけば、お金で大ケガをしない!」をコンセプトに、全50回のプログラムを配信しています。この番組では、学校の金融教育カリキュラムを作る際にも使用されている「金融リテラシー・マップ」にまとめられている項目を踏まえながら、金融知識をひとつずつ学んでいきます。
今回は、第6回の「給与明細には情報がたくさん!所得税とは」でお話した内容を記事としてお届けします。
所得税を学ぶために知っておきたい「所得」と「収入」の違い
今日のテーマは「所得税」です。前回に引き続き、給与明細を教材に学んでいきます。給与明細に記載されている控除には「社会保険料」と「税金」の2種類があり、前回は社会保険料について詳しく解説しました。本日は、もうひとつの控除である税金、その中でも「所得税」について教えてください。
「所得」に対して支払うのが「所得税」ですが、その前にまず、「所得」と「収入」の違いについて確認しておきましょう。この2つの違いはご存じですか?
なんとなく、同じ意味合いで使っていたかもしれません。
「税法」で定められている「所得」とは、「収入」から「必要経費」を差し引いた金額のことをいいます。給与を例にすると、控除される前の給与の額面が収入です。
実は、所得にはいろいろな種類があり、株式売却での「譲渡所得」、不動産を所持していれば「不動産所得」、副業の収入があれば「雑所得」など、10種類あるんです。今回テーマにしている「給与明細」に関係するのは、その中の「給与所得」ですね。
【参考】所得税法での所得の10種類
出所:国税庁「No.2011 課税される所得と非課税所得」
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
そんなにたくさんあるんですね。会社員の場合は、給与所得に対する所得税を支払っているということですね。
そうなります。給与所得以外にも収入がある場合には、それぞれに対して所得税が発生します。
NISAやiDeCoと所得税の関係とは
会社から給与をもらいつつ資産形成をしていると、例えば、株や投資で利益を得た人の所得税はどうなるのでしょうか。
資産形成をどのような形で行っているかによって異なりますが、追加で所得税がかかる場合ももちろんあります。
ちなみに、国がNISAやiDeCoを推進している理由のひとつにも、この所得税が関係しているんですよ。
詳しく教えてください。
通常の証券会社の口座で投資をすると、売却益や配当などには税金がかかります。ですが、NISAの枠で株式投資や投資信託を購入した場合、その売却での利益や配当には所得税がかからないんです。これがNISAの最大のメリットですね。
iDeCoは、受け取り方によっては所得税がかかることもありますが、制度内で売買する際に発生する売却での利益には所得税がかかりません。これは、税金の対象とならない「非課税所得」として扱われるためです。
さらに、iDeCoにはもうひとつのメリットがあり、掛け金の全額が所得税の控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となるんです。所得税に対しては節税の要素となります。このメリットは、年末調整などですでに経験している人もいらっしゃることでしょう。
資産形成や資産運用を考える上で、重要なポイントになりますね。
NISAとiDeCoの制度については、また別の回で詳しく解説します。
所得税の金額や税率はどう決まる?
それでは、給与にかかる所得税について詳しく見ていきましょう。所得税の金額や税率は、どのように決まるのでしょうか。
所得税は、1月から12月の1年間の給与所得に基づいて決まります。年間の総額というところがポイントになりますね。所得税の税率は「累進課税制度」を採用しており、給与額が多い人ほど税率が高くなる仕組みになっています。
給与明細に記載されている「所得税」は、毎月の給与所得を元に計算されていて、実は概算の金額なんです。月収がこの金額なら所得税はこの額、というように決められています。金額は国税庁のホームページで見ることができます。
なぜ概算になっているのでしょうか?
なぜなら、納める「所得税」の正確な金額は、年間の「給与収入」から「給与所得控除」「所得控除」の2つを差し引いた「課税所得」に基づき、さらに「税額控除」を考慮して算出されるものだからです。
【参考】税額控除の主な項目
出所:国税庁「No.1200 税額控除」
- 配当控除
- 分配時調整外国税相当額控除
- 外国税額控除
- 政党等寄附金特別控除
- 認定NPO法人等寄附金特別控除
- 公益社団法人等寄附金特別控除
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン)
- 住宅耐震改修特別控除
- 住宅特定改修特別税額控除
- 認定住宅等新築等特別税額控除
- その他青色申告者向けの特別控除がある
ちなみに、税額控除には住宅ローン控除などが含まれます。確定申告が必要となるケースもあるため、そちらも別の回で詳しくお話しします。
【参考】所得税額の決まる流れ
モニクルプラス編集部作成
【参考】課税所得レンジにおける税率
出所:国税庁「No.2260 所得税の税率」をもとにモニクルプラス編集部作成
年末調整で12月の給与が変わる理由
年末調整では、何を調整しているのでしょうか。
12月になると、1年間の給与額が確定しますよね。概算で税金の支払いをしているので、人によっては払いすぎていたり、逆に不足していたりすることがあります。そこで、その差額を12月の給与で調整するしくみになっているんです。
12月の振込額が変わるのは、そのような背景があるのですね。所得税は1年間の給与額で決まるということですが、給与は収入と手取りで金額が異なりますよね。どちらに税金がかかるのでしょうか。
実はどちらでもなく、税額は「課税所得」という金額によって決まります。課税所得とは、給与収入からさまざまな項目を差し引いた後の金額で計算されます。この差し引かれる項目には「給与所得控除」と「所得控除」があります。
給与収入から給与所得控除と所得控除を差し引いた金額が課税所得となり、それをもとに税率が決まり、所得税が決まるということですね。
そうです。
「給与所得控除」と「所得控除」
先ほどのお話に出ました「給与所得控除」と「所得控除」。名前が似ていますが、どう違うのでしょうか。
給与所得控除は、仕事を遂行する上で発生する費用を控除する制度です。例えば、スーツ代や文房具代など、仕事に必要な費用を自己負担することがありますが、そういった負担を軽減するために設けられているんです。
仕事を遂行する上で発生する費用、ということですが、何を買うのかは人によって異なりますよね?
そうですよね。そのため、給与所得控除は給与収入額に応じて金額が決められているんです。具体的な計算式や数字は、国税庁のHPに掲載されています。
【参考】収入金額レンジでの給与所得控除額
出所:国税庁「No.1410 給与所得控除」をもとにモニクルプラス編集部作成
それでは、「所得控除」とは何なのでしょうか。
所得控除は、全部で15種類あります。民間の保険会社の生命保険に加入していると「生命保険料控除」が適用されます。
所得控除は、年末調整の際に個人で申請するものですよね。毎年、契約している保険会社から年間保険料が記載された書類が届きます。
生命保険や損害保険など、さまざまな控除がありますね。こうしたプロセスを経て、12月に「源泉徴収票」を受け取ります。源泉徴収票には、年間の正確な給与額や税額が記載されているので、一度じっくり確認するのもいいかもしれません。
今回、改めて自分の源泉徴収票を見返してみたのですが、「こんな項目にこんなに支払っていたんだ」と改めて実感し、なかなか興味深かったです。
【参考】15種類の所得控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoの掛け金もここに含まれる)
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
出所:国税庁「No.1000 所得税のしくみ」
第6話のまとめ
- 給与明細に記載されている「所得税」は概算
- 正確な「所得税」は年末調整で決定する
- 「所得」には10種類あり、新NISAは非課税所得
パーソナリティー:泉田良輔プロフィール
株式会社モニクル
取締役 グループ戦略担当
泉田 良輔 Ryosuke Izumida
慶応義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。2013年3月、株式会社ナビゲータープラットフォーム(現:株式会社モニクルリサーチ)を共同設立し、取締役に就任(現在は代表取締役)。2018年11月、株式会社OneMile Partners(現:株式会社モニクルフィナンシャル)を共同設立し、取締役に就任。2021年10月、ナビゲータープラットフォームとOneMile Partnersの親会社として、株式会社モニクルを設立し、取締役に就任。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。東京科学大学大学院非常勤講師。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程修了。著書に「銀行はこれからどうなるのか」「Google vs トヨタ」「機関投資家だけが知っている『予想』のいらない株式投資法」など。















